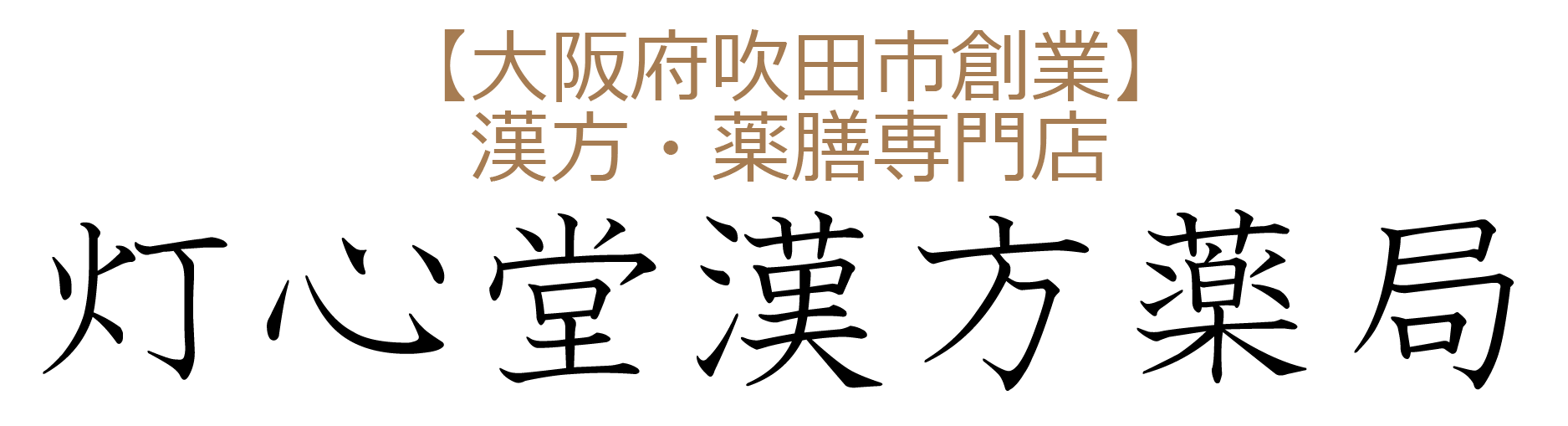漢方での血の働き~血が不足することで起こる症状、血のめぐりが悪いことで起こる症状とは?
目次
血の働き
漢方での血と西洋医学での血は考えが異なります。
西洋医学では血液といい、動物の血管内を循環する体液のことで、組織に酸素、栄養物質、ホルモンなどを供給し、炭酸ガス、老廃物などの排出物を運び去る働きがあります。
漢方の世界でも血は似たような考えです。
漢方での血とは?
漢方では西洋での血液に栄養・滋潤の働きが加わった考えとなっています。
そのため血が不足すると、顔色につやがなく、皮膚の乾燥、爪がもろくなり、筋肉のけいれんなどへと関連があります。
血虚
漢方において血とは、体に栄養を送り、潤す液体と考えられています。
血虚という血が不足する状態になると栄養不足や乾燥に関する多様な症状がでてきます。
・爪がもろい
・頭のふらつき
・目のかすみ
・筋肉のけいれん
・手足のしびれ
・動悸
・不眠
・驚きやすい
・生理の遅延
・生理量が少ない
・無月経
血は栄養を含んだ液体であるため、血虚になると顔色、口唇、爪、頭、目、筋肉に栄養が行きわたりません。
睡眠に関しては、血が充足していなければ気が戻る場所がなくなるため、不眠、多夢となります。
血に関することなどで生理にも影響を与えます。
血瘀、瘀血
血瘀(けつお)、瘀血(おけつ)ともいいます。
血が滞っている状態のことです。
気であれば気滞と表現しますが、血において滞りは血瘀といいます。
血の滞りがあるため、色も赤から紫色になり、血の滞りから腫れ、痛みにもつながってきます。
・夜間に悪化
・口唇や肌の紫暗色
・舌に瘀点、瘀斑
・腫瘤
・暗紫色の出血
・皮膚のガサガサ
・生理痛
・生理血の塊
・生理期間の延長
・無月経
血の滞りは、気滞とは異なり、移動しないため場所は固定され、刺すような痛みとなります。
血の滞りから口唇、肌、舌、手のひらに影響を与え、暗紫色、ガサガサへとなります。
血の滞りは生理にも反映され、生理痛や生理血に血の塊が多くみられるようになります。