この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら
西山光です


この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら




・補中益気湯はどういうときに服用したらいいの?
・合わない人っているの?
このようなお悩みに漢方薬局の薬剤師がお答えします。
この記事を読んでわかること
・補中益気湯の効能効果
・補中益気湯の構成生薬
・合う人、合わない人
・副作用、長期服用について
補中益気湯は疲労倦怠感、虚弱体質、食欲不振によく使用されます。
体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒
補中益気湯の効能効果(薬局製剤)
補中益気湯の効能効果はメーカーによっても異なるので、ご購入の際はしっかりパッケージを確認してください。
補中益気湯の効能効果を大きく分けると、疲労倦怠感などの体力回復系の働き、食欲不振の消化器系の働き、ねあせの皮膚系の効能効果があります。
・疲労倦怠感、病後・術後の衰弱などの体力回復系
・食欲不振、胃腸の働きの衰えの消化器系
・ねあせの皮膚系



補中益気湯の効能効果に、「体力虚弱で」「虚弱体質」「疲労倦怠感」「病後・術後の衰弱」と記載があり、身体の元気がないときに使う漢方薬だとわかります。
体力虚弱、虚弱体質、疲労倦怠感などの症状は「気虚」の状態といえます。
補中益気湯には人参・黄耆などの気を補う生薬が入っています。
補中益気湯が気を補うことで虚弱体質、疲労倦怠感、病後・術後の衰弱に効能効果があります。
効能効果に、「胃腸の働きが衰えて」、「食欲不振」とあるように補中益気湯は胃腸の働きを助けてくれます。
消化吸収の働きは漢方では気の働きと密接に関係があります。
補中益気湯に入っている人参・黄耆などの生薬が胃腸の働きを補ってくれます。
補中益気湯の効能効果に「ねあせ」とあります。
気がしっかりあれば、汗の穴を閉じることができます。
反対に皮膚の気が不足すると、毛穴を閉じることができなくなり、汗が漏れ出やすくなります。
補中益気湯に入っている黄耆という生薬は皮膚の気を補う働きがあります。
ねあせの効能の記載ある漢方薬は補中益気湯のほかに、桂枝加黄耆湯や玉屏風散などもありますが、それらにも黄耆は入っています。
補中益気湯の黄耆が皮膚の気を補うことで、汗が漏れ出ないようにし、ねあせに効能効果があります。
補中益気湯の効能効果に「感冒」とあります。
補中益気湯は気虚発熱という、気が不足したことで発熱したときに使用されることがあります。
通常の感冒と、補中益気湯がつかう感冒は異なるため、通常の感冒であれば葛根湯の方が適しています。
補中益気湯の「感冒」は身体が弱ることで発熱したときに適しています。
補中益気湯には人参、黄耆などの気を補う生薬が多く入っています。
補中益気湯には10種類の生薬が入っています。
人参、白朮、黄耆、当帰、陳皮、大棗、柴胡、甘草、生姜、升麻が入っています。
補中益気湯に入っている生薬を働き別にまとめてみました。
・気を補う働き:人参・黄耆・白朮・大棗・甘草・生姜
・気を上向きへ巡らせる働き:黄耆・柴胡・升麻
補中益気湯に入っている人参、黄耆、白朮、大棗、甘草、生姜は気を補う生薬です。
人参は気を補う代表的な生薬で、知っている方も多いと思います。高麗人参、朝鮮人参という言葉も聞いたことがあるかもしれません。



↑人参。漢方の人参はウコギ科の植物。普段、食べる人参はセリ科で、別の植物です。
補中益気湯で特徴的なのは黄耆(おうぎ)という生薬も入っていることです。漢方の世界では黄耆も、人参と並ぶ気を補う代表的な生薬です。
人参と黄耆の組み合わせは気を補うときによくみられ、人”参”と黄”耆”が入った漢方薬を参耆剤(じんぎざい)という言葉もあるくらいです。
補中益気湯には人参、黄耆などの生薬が気を補うことで、身体の働きを高め、元気づけ、胃腸の働きを助けてくれます。
補中益気湯は人参、黄耆の気を補う生薬を中心に構成されています。
補中益気湯には気を上に持ち上げる生薬が入っていることが一番の特徴です。
補中益気湯に入っている黄耆、柴胡、升麻は気を上向きにめぐらせる生薬です。



↑黄耆(おうぎ)。黄耆は気を補う働きと、気を上へ、表へ持ち上げる働きがあります。
気を上に持ち上げることで、下に落ち込んだ内臓・気を上に引っ張り上げます。
補中益気湯の効能効果に「元気がなく」とあるのは、気が下へ沈んでいる状態です。
補中益気湯が落ち込んで、気が沈んでしまった状態を上に持ち上げ、元気をつけてくれます。
補中益気湯は人参、黄耆などが気を補うことで、虚弱体質、疲労倦怠感、食欲不振などに効果を発揮します。
補中益気湯は黄耆、柴胡、升麻が気を上へ持ち上げることで、元気がない方に適した漢方薬になっています。



補中益気湯は気を補う漢方薬のため、気の不足からの疲労倦怠感などに適しています。
注意が必要なのは、疲労倦怠感というのは気の不足だけが原因でないことです。
例えば、しんどいときでも身体を動かすと楽になってきたな、と感じことはありませんか?
最初はけん怠感があっても、身体を動かすことで徐々に身体が楽になってくるのは気滞が原因と考えられます。
身体を動かすことで、疲労倦怠感が軽減するタイプは「気虚」ではなく、「気滞」の体質ため、補中益気湯は適していません。
「補中益気湯が効かない」という経験をされた方もいらっしゃると思います。補中益気湯が効かない理由としては、体質が気虚ではなく、気滞や他の体質の可能性があります。
| 合う人 | 合わない人 |
|---|---|
| ・動くと余計にしんどい方 ・胃腸の働きが弱い方 | ・動いた方が身体が楽になる方 ・胃腸の働きが衰えていない方 |
「補中益気湯は自律神経やうつに効きますか?」と質問があった場合、回答はNOです。
添付文書に、自律神経失調症、うつの効能効果が記載されていないためです。
しかし、漢方薬は病名でなく、体質でつかいます。
自律神経失調症、うつの結果として、「体力虚弱で、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすい方の疲労倦怠感」でお悩みであれば、補中益気湯はおすすめできます。
自律神経失調症といっても、症状は人それぞれ、体質も人それぞれです。
「自律神経失調症だから、この漢方薬がいい!」というものはありません。漢方薬は体質で選びます。漢方薬の効能効果と、ご自身の状態が合っていれば服用していただいて大丈夫です。
体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒
補中益気湯の効能効果(薬局製剤)
「補中益気湯は更年期に効きますか?」と質問があった場合、回答はNOです。
添付文書に、更年期障害の記載がないためです。
しかし、漢方薬は病名でなく、体質でつかいます。
女性の更年期であろうと、男性の更年期であろうと、症状として、「体力虚弱で、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすい方の疲労倦怠感」でお悩みであれば、補中益気湯はおすすめできます。
更年期といっても、症状はイライラから抑うつ、ホットフラッシュなど様々です。
「更年期だから、この漢方薬がいい!」というものはありません。漢方薬は体質で選びます。漢方薬の効能効果と、ご自身の状態が合っていれば服用していただいて大丈夫です。

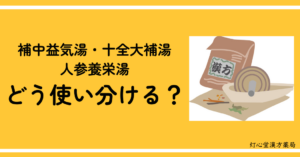
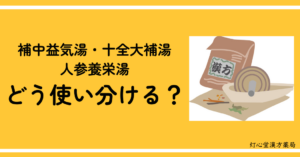
補中益気湯の副作用としては、皮膚(発疹・発赤、かゆみ)、間質性肺炎(空せき、息苦しさ)、偽アルドステロン・ミオパチー(けん怠感、筋肉痛)、肝機能障害(発熱、かゆみ、けん怠感、黄疸)などがみられることがあります。
これらの症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師又は薬剤師に相談をしてください。
漢方の長期服用にてよく問題になるのが、甘草です。
甘草を多くとっていると副作用が生じやすくなります。
メーカーにもよりますが、一般的に補中益気湯に含まれる甘草の量は1.5gです。
甘草の1.5gというのは多くはありませんが、ほかの漢方薬を併用したり、人によっては副作用がでたりすることがあります。
手足の脱力感、筋肉痛、しびれがみられるようになったときは甘草による副作用の可能性があります。
そのような症状がみられた場合は直ちに服用を中止してください。
・補中益気湯は体力虚弱で、元気がなく、胃腸が衰えて、疲れやすい方の疲労倦怠感などにつかいます。
・補中益気湯は気を補い、気を上向きにめぐらせる生薬から構成されています。
・補中益気湯は気虚、気が落ち込んだ方に適した漢方薬です。