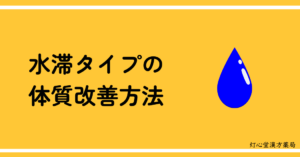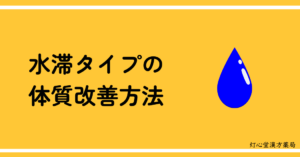この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら
西山光です


この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

漢方では「水」のことを津液、陰といいます。
漢方では「水」「津液」は身体を潤すうえでとても重要な役割があります。

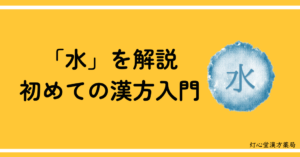
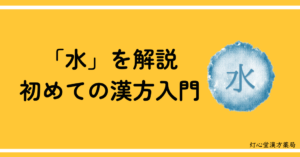
体液を不足した状態を漢方では陰虚といいます。
陰虚というと脱水症状のようなイメージがあるかもしれませんが、漢方での陰虚は幅広い意味合いです。
「体液」の不足を陰虚としているように、肺で陰虚になればせきがでたり、腸で陰虚になれば乾燥した便秘になったりします。
陰虚とは脱水のような全身症状だけでなく、身体の各部位でもみられます。
陰とは体を満たす水・細胞間液・分泌液のことのため、陰虚というのはそれらが不足している状態です。
陰虚になると、乾きに関する症状が多くあらわれます。
・口渇
・口唇の乾燥
・皮膚の乾燥
・尿が濃く少ない
・便が固い
・便秘
・舌の乾燥
・細脈
・ほてり
・のぼせ
陰虚からの渇きのため、口唇・皮膚・舌の乾燥となります。
腸も潤いがなくなるため便秘となります。
陰虚と水不足から、体を冷やす液体がないため、のぼせ・ほてりの症状がでます。
脈の血液の水分が不足するため、脈も細くなります。
陰を養う食べ物の特徴は、水水しく、優しい甘味のある食べ物です。
また白い食材も潤してくれます。
水水しいものは、潤いを助け、また優しい甘味は陰を補うのを助けます。
さらに酸味が組み合わさると効率的に陰を補うことができます。
陰虚タイプにおすすめの食べ物は、白菜、豆腐、梨、蓮根、白胡麻、ゆり根、白きくらげ、トマト、きゅうり、メロン、リンゴ、はちみつレモン、梅干しとごはん、酢豚、黄精、旱蓮草、女貞子、クコの実、沙参、玉竹などがあります。
白菜、豆腐、梨、蓮根、白胡麻、ゆり根、白キクラゲなどの白い食べ物は潤してくれます。
味もあっさりしており、優しく補ってくれます。
甘味が潤す働きがあり、酸味が引き締める働きがあります。
陰を補う上で、甘味と酸味の組み合わせにて相乗効果があります。
はちみつレモン、梅干しとごはん、酢豚などはとてもいい組み合わせです。
薬膳では、黄精、旱蓮草、女貞子、クコの実、沙参、玉竹などが有名です。
旱蓮草(かんれんそう)、女貞子(じょていし)の組み合わせは、中国では二至丸として有名で、陰を補う働きがあります。
枸杞の実も甘味があり、補ってくれます。
辛いものは水を発散する性質があるため、陰虚体質の方と相性がよくありません。
またお酒、タバコもNGです。
お酒は飲むと、のどが熱く感じるように熱の性質をもちます。
タバコも熱の性質をもつため、控えましょう。
陰虚のため、適度な水分が必要です。
過剰に摂取すると水毒になり、悪影響になるため、こまめに少量ずつ水分をとってください。
お酒を飲むとトイレが近くなった経験はありませんか?
お酒に含まれるアルコールは、身体からすると不要なもののため、それを追い出すために利尿に働きます。
利尿は、陰を排出することにつながります。
お酒の飲みすぎ、毎晩の飲酒は陰虚体質の方にはおすすめできません。
またお酒は飲むと、のどがカッーと熱くなります。
お酒には火の性質あると考えられ、アルコールによる利尿作用だけでなく、アルコールの火の性質からも陰を消耗しやすくなります。
火の性質があるのはお酒だけでなく、タバコも火邪の1種であり、陰虚には不適です。
漢方では、タバコの火邪の性質によって肺の陰を傷つけまると考えられます。
タバコの火邪によって肺の陰がどんどん不足していくと、肺は水分を保持できず、スカスカになり、スポンジ状になります。
タバコによってスポンジ状になった肺では常に息苦しい状態が続くようになり、最近ではCOPDといわれることもあります。
COPDを漢方で考えると肺の陰虚と捉えることができます。
陰虚の症状から選び、酸棗仁湯、帰脾湯、滋陰降火湯、潤腸湯、麻子仁丸、麦門冬湯、六味丸、知柏地黄丸、清暑益気湯などがあります。
腸が陰虚で潤いがなくなることで、便が乾燥し、出しにくく、便秘となります。
乾燥した便です。
腸を潤し、便通を改善する漢方薬に麻子仁丸、潤腸湯があります。
麻子仁丸(ましにんがん)は麻子仁という生薬が潤腸し、便通を改善します。
「仁」は植物のタネを意味し、タネにはオイルが豊富に含まれています。
麻子仁のオイルにて腸を潤し、便通を改善します。
麻子仁丸には杏仁も入り、肺・大腸の気のめぐりを改善しつつ、杏「仁」の油分にて腸を潤し、排便を助けます。
潤腸湯(じゅんちょうとう)はまさに腸を潤す漢方薬になっています。
潤腸湯は麻子仁丸にさらに潤す生薬を足した漢方薬です。
麻子仁・杏仁だけでなく、桃仁も入り、当帰・地黄も加わり、腸を潤す働きは強いです。
当帰・地黄は肌も潤す働きがあるため、便秘と肌の乾燥があるときは潤腸湯が適しています。
肺が陰虚で潤いがなくなることで、のどに潤いがなく、痰が切れにくく、咳き込むようになります。
肺を潤し、のどを潤し、渇いた痰を潤し、痰を出しやすくする漢方薬に麦門冬湯、滋陰降火湯があります。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)は潤す生薬と痰を出す生薬から構成されています。
麦門冬、人参、粳米、甘草はすべて甘味の生薬で、胃を潤し、肺を潤します。
肺を潤すことで、のどの渇き、からぜきを緩和します。
麦門冬湯の半夏(はんげ)という生薬が、痰を出し、痰が気にくいときにも有効です。
滋陰降火湯は、麦門冬湯よりも潤す生薬が多く入っています。
滋陰降火湯の当帰・地黄・天門冬・麦門冬・知母・甘草は潤す生薬で、滋陰する働きがあります。
滋陰降火湯の潤し、冷やす働きは麦門冬湯よりも強く、肌の乾燥、便秘などもあるときは滋陰降火湯の方が適しています。
腎陰という体全体を冷やす陰が不足することでほてりが生じます。
腎は排尿をコントロールしている臓腑であり、腎陰の不足は頻尿にもつながります。
腎陰を補い、ほてりを鎮め、頻尿を抑える漢方薬に知柏地黄丸があります。
頻尿と肺陰虚によるからぜき、息切れがあるときは五味子・麦門冬を加えた味麦地黄丸があります。
麦門冬が肺胃を潤し、五味子がそれを引き締めることで陰が漏れ出ていかないように防ぎます。
頻尿とからぜきがあるときは味麦地黄丸が適しています。
心陰虚・心血虚になると不眠症、精神不安、いらだちが生じます。
心の渇きは不眠や精神症状の原因です。
心陰・心血を補い、不眠症につかう漢方薬に酸棗仁湯・帰脾湯があります。
酸棗仁湯(さんそうにんとう)には酸棗仁が大量に入っており、酸棗仁が心陰・心血を養ってくれます。
心陰を補い、心身の疲れ、精神不安、不眠症につかいます。
帰脾湯は心陰・心血と気を補う漢方薬です。
帰脾湯にも酸棗仁がはいっており、さらに人参・黄耆も入り、気を強く補ってくれます。
胃腸の弱さ、心身の疲れ、不安、いらいら、不眠症があるときは帰脾湯が適しています。
夏の暑さにやられ、気や陰を消耗した暑気あたりにつかう漢方薬に清暑益気湯があります。
清暑益気湯(せいしょえっきとう)は字の通り、暑さを清め、気を益する漢方薬です。
清暑益気湯には人参・麦門冬・五味子の組み合わせが入っています。
人参・麦門冬は陰を補う重要な生薬であり、潤す働きが強いです。
五味子は酸味の強い生薬で、酸味によって気・血・水が漏れ出ていかないように収斂し、引き締める働きがあります。
夏の暑さで失われた水を人参・麦門冬・五味子が補います。
さらに黄耆の補気の生薬、黄柏の熱を冷ます生薬も入り、暑気あたりに適した漢方薬が清暑益気湯です。