この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら
西山光です

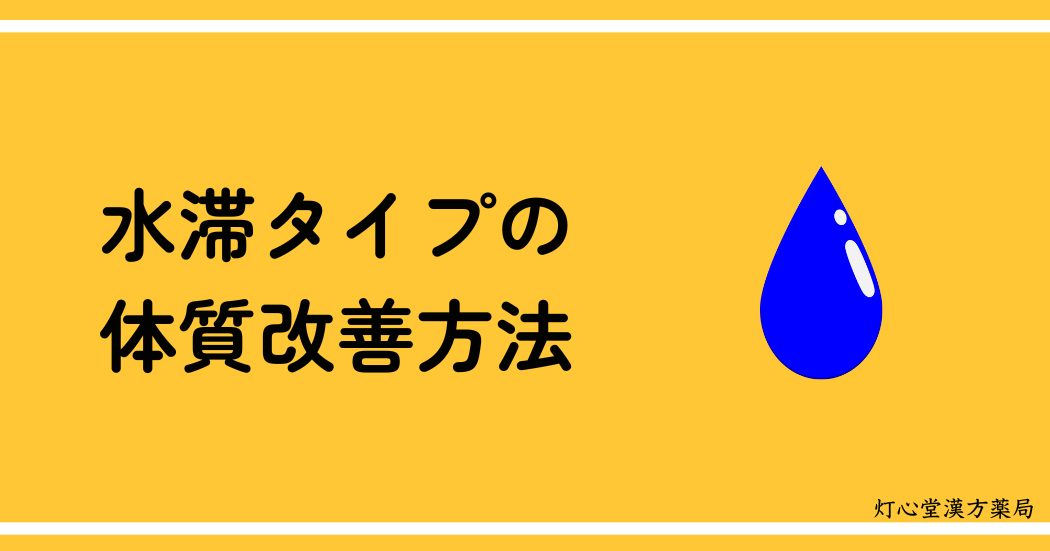
この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

漢方では「水」は身体を構成する重要な要素の1つです。
「水」「津液」があることで、身体に潤いがあります。
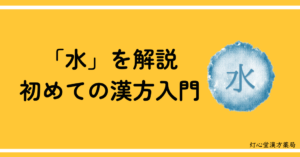
漢方では「水」「津液」でもサラサラした水なのか、ドロドロした水なのか、違うものと考えます。
サラサラした水なのか、粘性のあるドロドロした水なのか、しっかり見極める必要があります。
水滞とはサラサラした水が鬱滞し、溜まっている状態です。
水の貯留によって、水に関連した様々な症状があらわれます。
・むくみ
・めまい、動悸
・うすい痰
・鼻水
・水様性の嘔吐
・胃内停水
・下痢
・浮腫
水滞の場合はサラサラした水が溜まっているため、鼻水もサラサラした鼻水です。
痰飲とはネバネバした水が溜まっている状態のことをいいます。
水の停滞は、時間の経過とともに鬱熱を生じ、水が煮詰められ、粘性をもってきます。
水の停滞であればサラッとした水ですが、時間の経過や熱を帯びることでネバっとしたヌメリのようになってきます。
粘性をもった水のことを漢方では痰といいます。
イメージしやすい例としては、カゼの初期はサラサラした鼻水ですが、時間の経過とともにネバネバした鼻水になっていきます。
カゼひいたときの痰もはじめはサラッとして出しやすいですが、時間の経過とともに粘性を持ち、痰を出しにくくなります。
サラサラした水を追い出す生薬と、ネバネバした痰を出す生薬は違ってきます。
痰というとのどに溜まる印象があると思いますが、漢方では全身に溜まる可能性があり、様々な症状を呈します。
・咳嗽
・喀痰
・めまい
・ふらつき
・悪心、嘔吐
・しこり
・しびれ
・関節痛
痰がのどにあることで、咳き込みやすくなります。
痰によって気血の流れが邪魔されると、めまい、ふらつきになります。
痰や水は実体があるものであり、痰が結することでしこりになります。
わかりやすい例としてはニキビがあります。
痰湿がたまることでニキビになります。
痰湿が関節に溜まり、気血の流れを邪魔することで関節痛、しびれみなります。
ヒザに水が溜まるもの、漢方では痰湿と考えることができます。
痰湿を出す食べ物の特徴は、味があっさりしているものです。
淡味は利水に働くといわれ、漢方での水をめぐらせる生薬も味がアッサリしているものがほとんどです。
痰湿タイプにおすすめの食べ物は、とうがん、大根、カブ、ごぼう、グリンピース、枝豆、大豆、豆腐、コンブ、ワカメ、ヒジキ、あずき、スイカ、バナナ、トウモロコシのヒゲ、ハトムギ、シロネ、ちんぴ、綿茵蔯などがあります。
とうがんは痰湿タイプにとても合った食べ物です。
漢方では主に冬瓜の種を使用しますが、冬瓜は痰湿タイプにおすすめです。
とうがん、大根、かぶ、ごぼう、グリーンピース、大豆など味が淡いです。
コンブ、ワカメ、ヒジキなどの海藻類は塩味があり、固く凝り固まったものをほぐす働きがあります。
薬膳では、トウモロコシのヒゲ、ハトムギ、シロネ、ちんぴ、綿茵蔯などが有名です。
トウモロコシのヒゲは漢方では南蛮毛ということもあります。
ハトムギは漢方ではヨクイニンという名前でよく使用されます。
ちんぴはミカンの皮です。ちんぴも漢方でよく使用されます。
気の不足があると、余分な水を排出する力も弱まります。
胃腸の働きを重たくするものは相性が良くありません。
脂っこいものはベットリしているように痰湿をため込みます。お酒や味が濃いものも避けるのがベター。
身体に水が溜まっているため、運動することはおすすめです。
運動することで汗をかき、水の循環がよくなります。
運動でしっかり呼吸をすることで、肺気がめぐり、水の流れもよくなります。
呼吸をしっかりし、汗をかく有酸素運動がおすすめです。
ただし、汗をかいたあとはしっかり水分補給してくださいね。
水滞の症状から選び、五苓散、二陳湯、苓桂朮甘湯、小青竜湯、防已黄耆湯、温胆湯、当帰芍薬散、半夏白朮天麻湯、茯苓飲、半夏厚朴湯、分消湯、補気建中湯、麻杏甘石湯、五虎湯、麻杏薏甘湯、薏苡仁湯などがあります。
水が身体に停滞することで浮腫みになります。
浮腫みにつかう漢方薬に五苓散、防已黄耆湯、当帰芍薬散、分消湯、補気建中湯などがあります。
五苓散は利水の生薬が多く入り、水のめぐりを改善します。
防已黄耆湯は身体の表面の水のめぐりを改善し、多汗症などにもつかわれます。
当帰芍薬散は血を補う生薬も入り、生理不順と浮腫みのある方に適しています。
分消湯には水を追い出す生薬が多く入り、利水の生薬の種類は一番多く入っています。
補気建中湯は、身体が弱ることで水がたまりやすい体質の方向けの漢方薬です。
鼻で水滞があることで、鼻水、鼻炎となります。
鼻を温め、乾かす漢方薬に小青竜湯があります。
小青竜湯には温めて乾かす生薬が多く入っています。
小青竜湯に入っている麻黄・乾姜・桂皮・半夏・細辛は温める生薬で、水を発散し、花粉症やアレルギー性鼻炎の鼻水の症状を緩和します。
とくに麻黄・桂皮の組み合わせはよく水を追い出します。
小青竜湯は温める働きが強いため、石膏という冷やす生薬を加え、温と寒で相殺し、水はけをよくする働きに特化したものに小青竜湯加石膏というものがあります。
小青竜湯加石膏はとても良い漢方薬なのですが、医療用にも市販にもなく、薬局製剤の煎じ薬としてのみ販売されています。
麻黄と桂皮は相性がよく、水を去る働きが強いのですが、麻黄と石膏も相性がよく、水を追い出す働きが強いです。
小青竜湯加石膏は麻黄・桂皮、麻黄・石膏のどちらの組み合わせも入った漢方薬のため、鼻炎、アレルギー性鼻炎にとても適した漢方薬で、市販されていないのが残念です。
気管支に炎症が起こり、浮腫むことで呼吸がしづらくなります。
気管支炎やぜんそくの漢方薬に麻杏甘石湯、五虎湯があります。
麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)は麻黄・石膏の組み合わせが浮腫んでいる水を追い出します。
麻杏甘石湯の杏仁が肺の気をめぐらせ、咳を抑えます。
麻杏甘石湯に痰切りの桑白皮という生薬を足したものが五虎湯といいます。
痰もからむ、せき・ぜんそくには麻杏甘石湯よりも五虎湯が向いています。
水の鬱滞が気血の流れを邪魔することで、頭まで気が行き届かず、めまいとなります。
めまい、動悸の漢方薬に苓桂朮甘湯、半夏白朮天麻湯があります。
苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)は茯苓・白朮が水のめぐりを改善し、めまいの原因となる余分な水を追い出します。
桂皮も入り、陽気を補うことで、水が流れやすいように助けます。
苓桂朮甘湯はめまいに頻用される漢方薬です。
半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)もめまいにつかう漢方薬です。
半夏白朮天麻湯の場合は、胃腸が弱さが原因で、水滞・痰湿が溜まりやすくなり、めまいとなります。
半夏白朮天麻湯には人参・黄耆の気を強く補う生薬が入り、胃腸の働きを助けます。
半夏・蒼朮・陳皮・沢瀉の生薬が水滞・痰湿を出し、めまいの要因を取り除きます。
半夏白朮天麻湯は胃腸の働きを助けつつ、めまいの要因の水滞・痰湿も追い出し、めまいに効果を発揮します。
痰湿の鬱滞があることで、気が本来あるべきところに流れることができず、精神不安や神経症、不眠などの症状がでることがあります。
痰湿からくる不安、神経症の薬に半夏厚朴湯、温胆湯があります。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)は気の鬱滞と痰湿を去る漢方薬です。
気滞と痰湿があわさることで、気のめぐりが悪くなり、不安になりやすくなります。
気の鬱滞と痰湿があることで、のど・胸のあたりのつかえ感が生じます。
不安と、のど・胸のつかえ感を半夏厚朴湯の半夏・厚朴・蘇葉が追い出します。
温胆湯(うんたんとう)は痰湿を取ることに特化した漢方薬で不眠症・神経症につかいます。
温胆湯には半夏・竹茹が入り、痰湿を取る働きが強いです。
温胆湯は痰湿をとることで、気血の流れが正常になり、胃腸が弱い方の不眠症・神経症につかいます。
胃に水滞・痰湿があることで胃腸の調子が悪くなります。
水滞による胃の不調に茯苓飲、痰湿による胃の不調に二陳湯をつかいます。
お腹に水が溜まり、チャポチャポするような方、水滞が込みあがってくることで呑酸、胃酸の逆流、胸やけにもなります。
胃に溜まった水の流れを改善する漢方薬に茯苓飲があります。
茯苓飲には茯苓・白朮の水を追い出す生薬が入っています。
人参も入り、胃腸の働きを補い、枳実・陳皮が鬱滞している水を下向きにめぐるように助けます。
胃に溜まった水によるはきけ、胸やけには茯苓飲があります。
お腹に水が溜まり、胃部不快感があるときは痰湿がたまっていることもあります。
痰湿は粘性をもった水のため、舌の苔も白く厚いものがつきやすくなります。
二陳湯には陳皮・半夏という痰湿を追い出す生薬が入り、胃部不快感のあるときにつかいます。
痰湿が関節に溜まることで関節痛となります。
痰湿による関節痛につかう漢方薬に麻杏薏甘湯、薏苡仁湯があります。
痰湿と関節痛を考えるうえでは、薏苡仁(よくいにん)という生薬が不可欠です。
薏苡仁が痰湿というヌメリをとり、通利し、関節痛につかいます。
麻杏薏甘湯と薏苡仁湯の違いは、麻杏薏甘湯(まきょうよくかんとう)は日の浅い関節痛につかい、慢性化したときは薏苡仁湯(よくいにんとう)が向いています。
