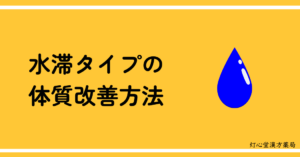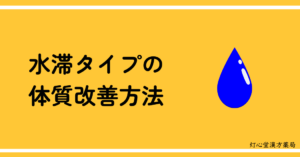この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら
西山光です


この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

漢方では「気」「血」「水」が身体を構成する要素として知られています。
ここでは「水」について解説します。
漢方での「水」は一般的に津液(しんえき)ということが多いので、「水」のことを津液と表現しています。
津液(しんえき)とは、漢方において生体における水液のことをあらわします。
津液というのは、臓器・組織に含まれる液体だけでなく、細胞間液・リンパ・分泌物なども含まれます。
津液は細かく分けると、津(しん)と液(えき)にわけられることもありますが、津液ということが多いです。
津の方が薄い希薄な液体で、液の方が形のある液体となります。
津液は身体を滋潤し、濡養する働きがあります。
「血」にも身体を潤す働きがあり、「潤す」という点では「血」も「津液」も同じといえます。
ただ「血」の方が栄養が豊富であるため、ドロッとした潤いになり、津液の方がサラッとし、眼・鼻・口・舌などを潤し、保護しています。
津液が足りなくなると乾燥に傾き、津液が停滞するとむくみなどに影響してきます。
津液は、漢方用語としても、一般的な意味合いでも、乖離が少なく、イメージしやすいです。
津液を不足した状態を陰虚と漢方では表現します。
津液とは体を満たす水・細胞間液・分泌液のことのため、陰虚というのはそれらが不足している状態です。
陰虚になると、乾きに関する症状が多くあらわれます。
・口渇
・口唇の乾燥
・皮膚の乾燥
・尿が濃く少ない
・便が固い
・便秘
・舌の乾燥
・細脈
・ほてり
・のぼせ
陰虚からの渇きのため、口唇・皮膚・舌の乾燥となります。
腸も潤いがなくなるため便秘となります。
陰虚と水不足から、体を冷やす液体がないため、のぼせ・ほてりの症状がでます。



水滞、痰湿というの、身体に過剰に水が溜まっている状態です。
ただし、注意点が1つあり、漢方では「水」に種類があり、使う生薬を使い分けます。
サラサラした水が溜まっていることは「水滞」「水飲」といい、粘性をもったドロドロした水が溜まっているときは「痰湿」といいます。
水滞、水飲とは、サラサラした水が溜まっている状態です。
鼻水で考えると、サラサラした鼻水は水滞、水飲の鼻水になります。
水の貯留によって、様々な症状があらわれます。
・むくみ
・うすい痰
・鼻水
・水様性の嘔吐
・胃内停水
・下痢
・浮腫
・胸水
・腹水
過剰な水によってむくみ、鼻水がでやすくなり、腸では下痢、胸では胸水、お腹では腹水となります。
痰飲というのは粘性をもった水のことを指し、それらが溜まった状態を痰湿といいます。
水が長い期間停滞し、熱をもってくると、粘性をもった痰といわれる状態になります。
日常生活で痰というと、のどに絡まるものをイメージしますが、漢方では痰が全身にたまります。
のどに痰が停滞すれば痰になり、脳に痰が停滞すればめまい・ふらつきになり、関節に痰が停滞すれば関節痛になります。
・咳嗽
・喀痰
・めまい
・ふらつき
・悪心、嘔吐
・しこり
・しびれ
・関節痛
痰湿はヌメリであるため、気の流れを強く邪魔します。
当然、水飲と痰飲とではつかう生薬も異なってきます。
水の停滞といっても、さらっとした水なのか、粘性をもった水なのか、症状、舌、脈から判断していきます。