この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら
西山光です

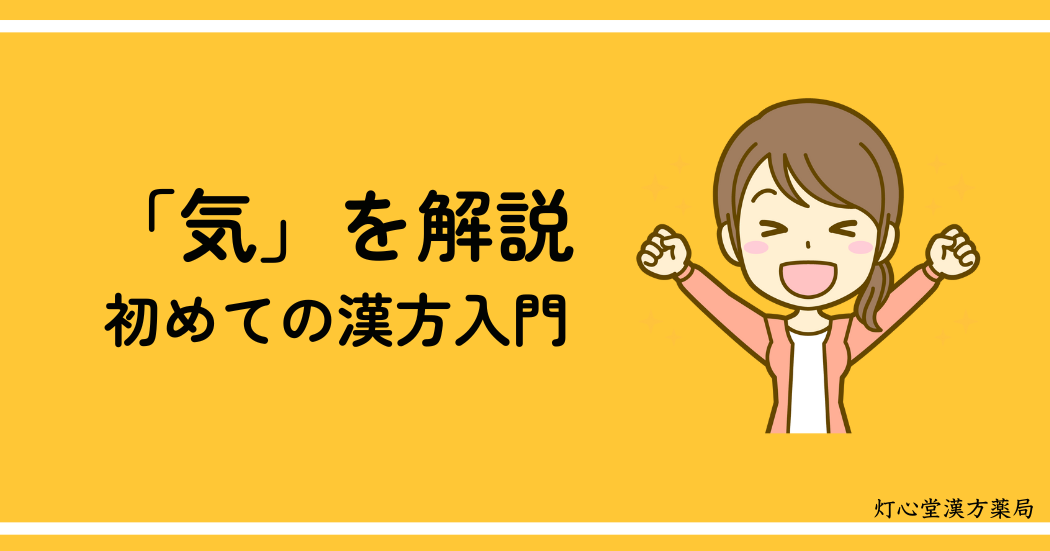
この記事を書いた人
・灯心堂漢方薬局 薬局長
・薬剤師歴10年以上
・店舗のLINE登録者数1000人以上
・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

ここでは漢方薬で使われる「気」という用語について解説します。
「気」の概念はとてもイメージが難しいです。
なぜなら、気は「質有りて形なし」といい、「気」の働きのものはありますが、実際に形としてみえるものではありません。
この記事を読んでいただき、そういった「気」について少しでもイメージをできるようになればと思います。
「気」とは「身体の働き」という言葉に置き換えることができます。
「気虚」は「身体の働き」が衰えている状態のため、元気がない、食欲がないなどの症状がみられ、「気滞」は「身体の働き」に滞りが生じているので、イライラ、便秘などの症状がみられます。
「気」とは物ではなく、身体の機能のことを「気」と表現しています。
漢方において気は大きく5つの働きがあります。
・血液・水をめぐらせる(推動)
・体をあたためる(温煦)
・免疫(防御)
・血液などを漏らさないようにする(固摂)
・気血水精を変換(気化)
気の働きによって血液・水が正常に循環します。
気が弱っていると、血液・水が循環せず、冷えやむくみなどにつながります。
気は陽の気であり、体を温める働きがあります。
冷え性は気の温める力が弱っているといえます。
気は免疫とも関連があります。
外から入ってきた悪いものと戦う働きがあります。
元気がないときは、調子も崩しやすいですよね。
気によって血液・汗などは血管などから漏れないように働きます。
気が弱っていると血液が血管から漏れ出て、あざができやすくなります。
運動による汗は正常なものですが、風邪ひいたときや少し動いただけで汗をかいてしまうのは気が弱っている症状です。
気によって、気血水精を互いに変換しています。
気の不調には大きく2種類あります。
気が不足している「気虚」と、気の働きに滞りのある「気滞」です。
「気」は「身体の働き」をあらわし、「気虚」とは「身体の機能」が落ちている状態のことです。
身体の機能が落ちているというと、どういった症状が想像できますか?
身体の機能が落ちると、元気がない、食欲不振、お腹が緩くなるなどの症状がでてきます。
また前述した、気の5つの働きも機能できなくなります。
・元気がない
・声に力がない
・息切れ
・食欲不振
・消化不良
・軟便
このようなときには気を補う必要があるため、いわゆる人参が入った漢方薬がよくつかわれます。

気滞というのは文字の通り、気が滞っている状態のことです。
「気」を「身体の働き」と考えると、「気滞」とは「身体の働きが滞っている状態」のことです。
身体の機能に滞りがあると、腸のめぐりが悪くなり、便秘や、精神的な不調がでやすくなります。
・張った痛み
・発作的な症状
・ゆううつ
・いらいら
鬱滞している気が原因であるため、気をめぐらせる必要があります。

「気」とは、「身体の働き」のことを表現しているため、「気」を実際に見ることはできず、物質として存在しないため、イメージが難しいです。
「気」は「身体の機能」のことのため、「気」の働きは気血をめぐらせたり、免疫の防御、身体を温める働きなどがあります。