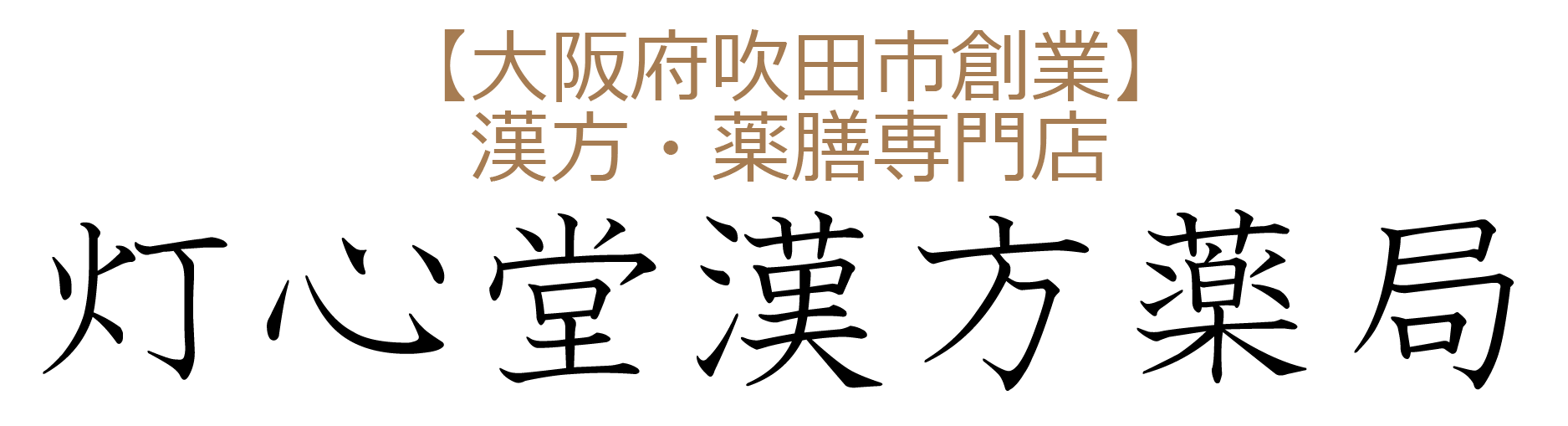【漢方】口が甘い2つの体質
とくに原因がないのに口が甘いと感じている方はいませんか?
味覚障害として考えると原因としては,亜鉛欠乏,糖尿病,腎不全などの全身疾患,感冒,舌粘膜疾患,心因性などが挙げられます。
甘いと感じるのには、糖尿病、ケトン症もあります。
ここでは漢方での口の甘味についての考え方と説明します。
漢方では五臓と味につながりがあります。
・肝と酸味
・心と苦味
・脾と甘味
・肺は辛味
・腎と塩辛味
漢方では口の甘味は脾の熱と考えられています。
脾というのは西洋医学の脾臓とは異なり、消化吸収機能全般のことを漢方では脾といいます。
脾は甘味とつながりがあり、脾の熱によって口の甘味となります。
脾の熱がこもるタイプに2つ種類があります。
・脾胃熱蒸(食欲あり、水を欲する)
・脾胃気陰両虚(食欲なし、水はあまり欲さない)
・脾胃気陰両虚(食欲なし、水はあまり欲さない)
それぞれの状態について説明します。
脾胃熱蒸
辛いもの、脂っこいもの、甘いものなどを食べ過ぎることで体に熱がこもります。
その熱が脾に停滞し、口に向かうことで口の甘味となります。
・口の甘味
・口渇し、水分を欲する
・多食
・口内炎
・便が固い
・尿が黄色い
・口渇し、水分を欲する
・多食
・口内炎
・便が固い
・尿が黄色い
これらにあてはまるときは脾胃熱蒸の体質の可能性があります。
このようなときは脾胃にたまっている熱をとる漢方薬をつかいます。
脾胃気陰両虚
加齢や、疲労や慢性的な不調によって脾胃の気と水を消耗している状態です。
水が不足しているため、熱を冷やすことができずに相対的に脾に熱がこもり、口の甘味となります。
・食欲不振・口渇するが、水はそこまで欲さない
・元気がない
・腹満
・息切れ
・疲れやすい
・軟便
・元気がない
・腹満
・息切れ
・疲れやすい
・軟便
これらにあてはまるときは気陰両虚の体質の可能性があります。
乾燥している脾胃を潤す漢方薬をつかう必要があります。
関連情報